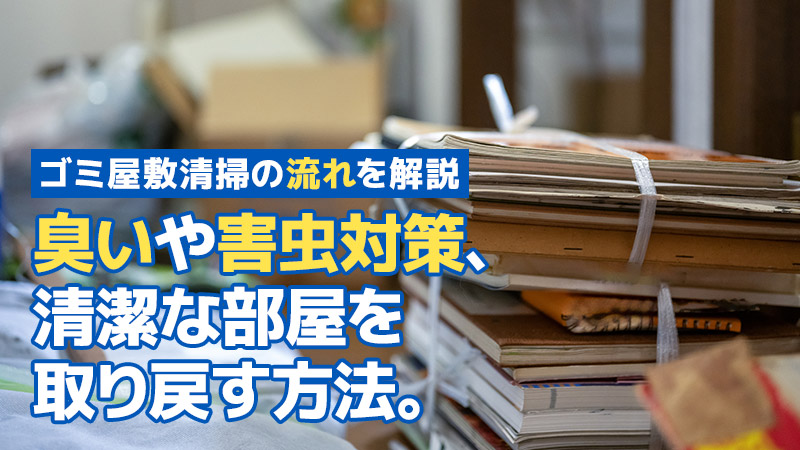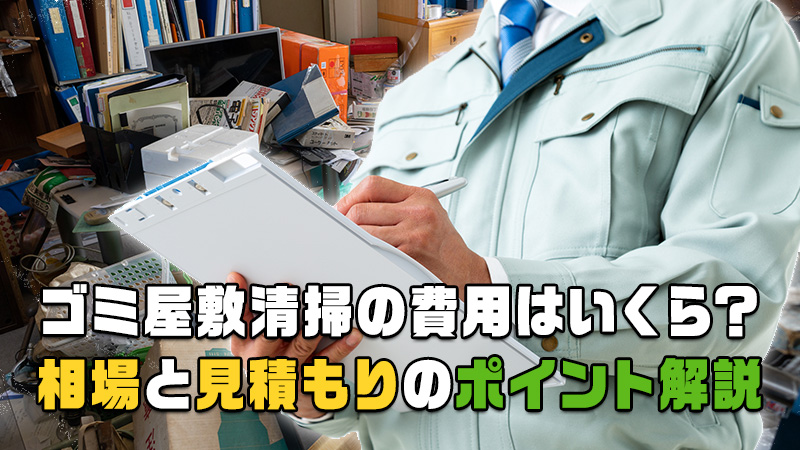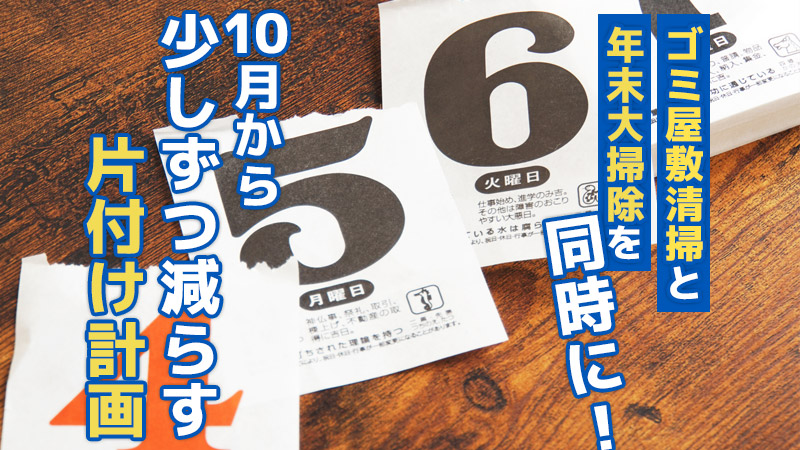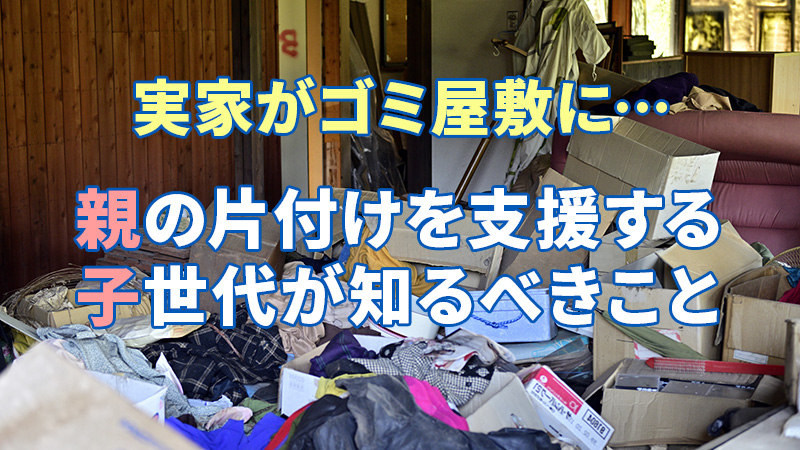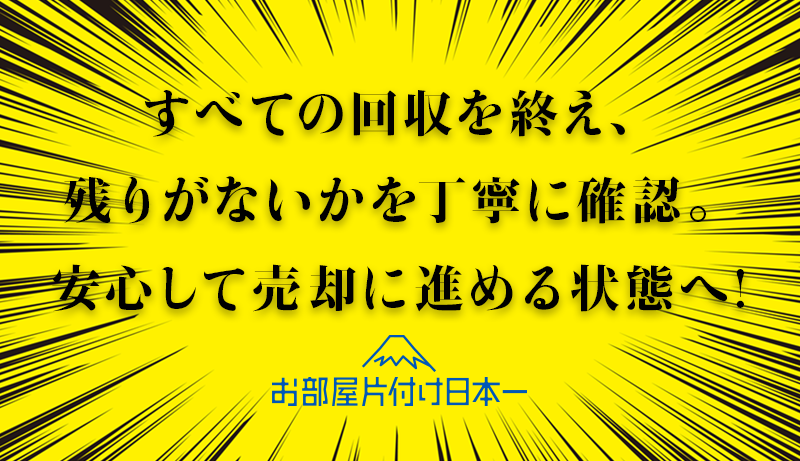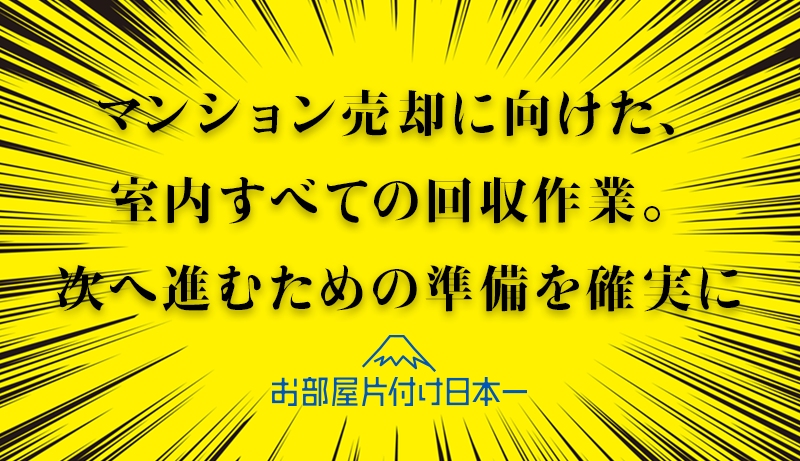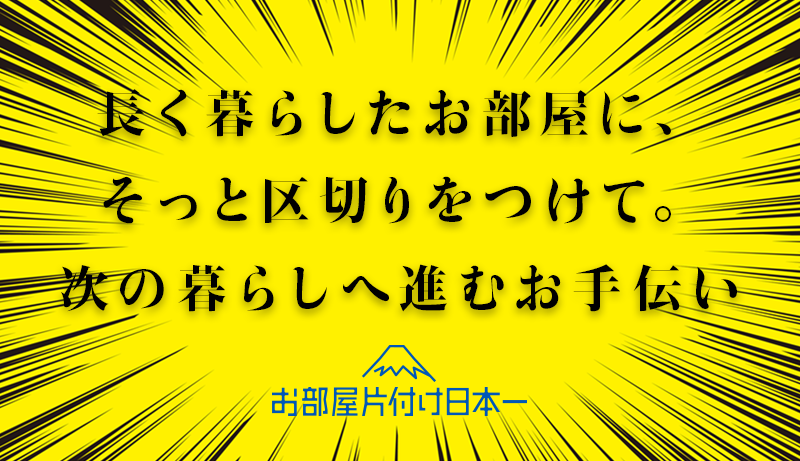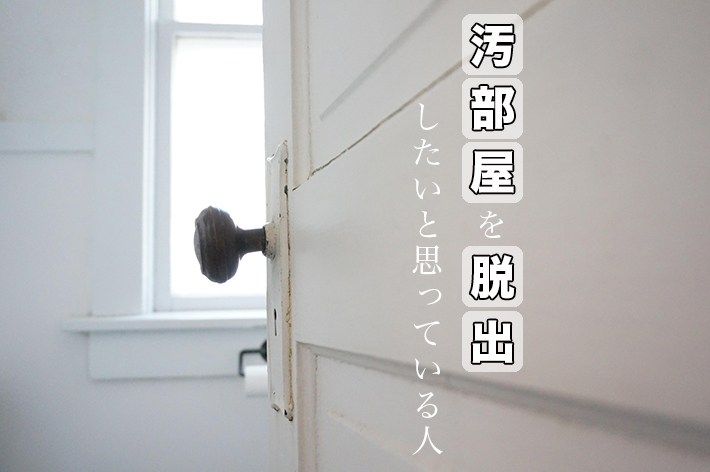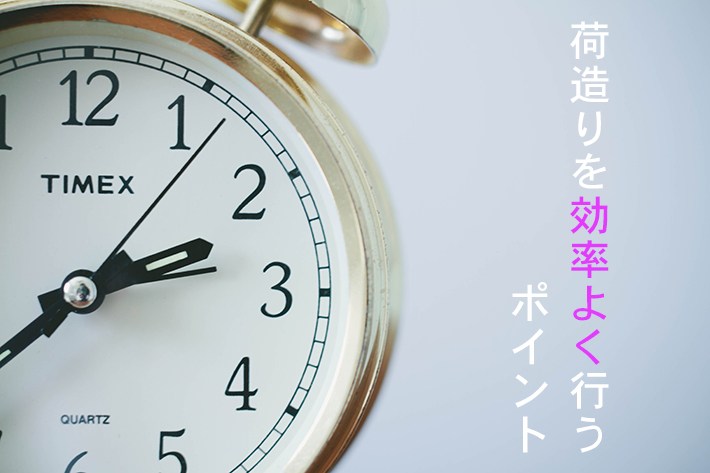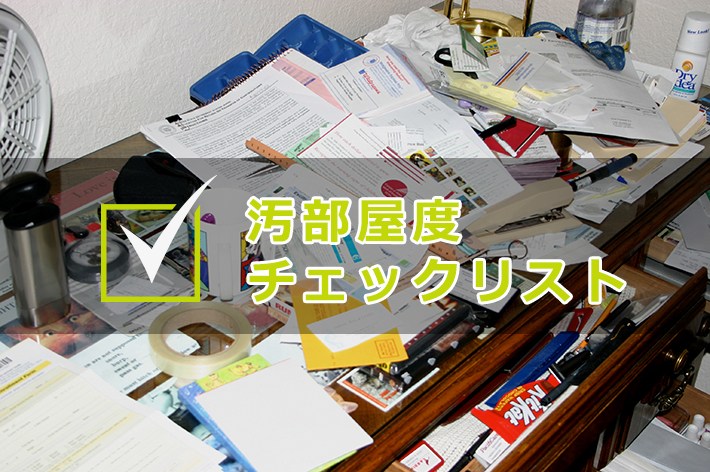「ちょっと散らかってるだけ…」
そう思っていた部屋が、いつの間にかゴミ袋を置く場所もないほどになっていませんか?
仕事が忙しくて。気力が出なくて。
気づいたら「どこから手をつけていいかわからない」状態になっていた。
実は、そんな悩みを抱えている人は少なくありません。
でも安心してください!
ゴミ屋敷の片付けは、“レベル”に応じて進め方を変えれば、自力でも十分に立て直せる場合があります!
この記事では、片付けのプロが見てきた現場の経験をもとに、あなたの状況に合わせた「レベル別の片付けステップ」と「現実的な片づけ方法」をわかりやすく紹介します。
目次
1.まずは「今の自分のレベル」を知ることが第一歩
部屋が散らかる理由は、人によってさまざま。
仕事のストレス、生活リズムの乱れ、家族との同居──
原因は違っても、共通しているのは「気づいた時には手がつけられなくなっている」ということです。
でも、焦らなくて大丈夫!
大切なのは、「どれくらいの状態なのか」を知ることです。
それがわかれば、必要なステップも、頼るべきタイミングも自然に見えてきます。
ここからは、ゴミ屋敷の状態を4つのレベルに分けて、それぞれに合った「現実的な片付け方法」を紹介していきます。
ゴミ屋敷レベル1:床が見える軽度な散らかり
まだ“片付け”でリカバリーできる状態

「最近ちょっと散らかってきたな…」と思ったら、それはレベル1。
床が2/3以上見えているなら、自力で完全に片付けできます!
お部屋の状況イメージ
- 床や机の上にモノが散らかっている
- 床や机の上にモノが散らかっている
片付けのコツ
- 収納よりも“不要なモノを減らす”ことを優先
- 迷ったら自分のルールを決める。「3カ月以上使用していなければ処分する」など。
ゴミ屋敷レベル2:散らかりが広がり、手が回らない状態
“自力片付け+部分サポート”で改善できる
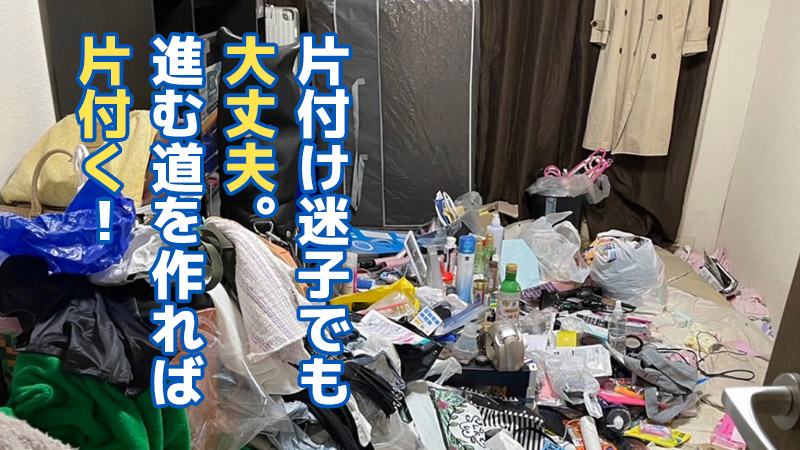
床がほとんど見えず、モノの山ができている状態。
服や書類、飲みの残しのペットボトルなどが混在していても、まだ自力で回復可能な範囲です。
お部屋の状況イメージ
- 通路はあるが、床の半分以上が見えない
- 匂いやホコリが気になり始める
- 作業は2〜3日規模
片付けのコツ
- 通路や玄関など“出入り口”から始める
- 分別袋を複数用意して同時並行で分ける
- 「仕分けだけ」専門業者に頼むのも効率的
ゴミ屋敷レベル3:山積み・層になったゴミの中で生活
“自力分別+業者サポート”が現実的な選択

部屋の中に足を踏み入れるのも一苦労。
床一面にモノが積み上がり、まるで「層」になっている──。
この状態は、精神的にも体力的にも、自力だけでは難しい段階です。
それでも、完全に諦める必要はありません。
「自分でできる部分」と「業者に任せる部分」を分けることで早期に解決できます。
お部屋の状況イメージ
- 床が完全に見えず、生活ゴミやモノが層になっている
- ゴミの下に何があるかわからない
- 匂いやカビ、害虫が発生していることも…
- 作業期間は数日〜1週間程度
片付けのコツ
- “通路の確保”を最優先に。まずは出入り口から動線を作る
- 「残したい物リスト」を先に作成しておくと効率的
- 危険物・大型家具・家電の搬出は専門業者に任せる
- 体力・気力の負担を減らすため、1日1時間の部分片付け+プロ併用がおすすめ
ポイントアドバイス
片付けを始める前に、「どの範囲を自分でやるか」を決めておくことが大切です。
例えば「キッチン周りは自分で、寝室と廊下は業者に」と線を引くだけで、気持ちが楽になります。
一度に全部やろうとせず、“一部ずつ取り戻す”感覚で進めていきましょう。
ゴミ屋敷レベル4:悪臭・害虫・腐敗が進行した状態
衛生リスクが高く、自力作業は危険
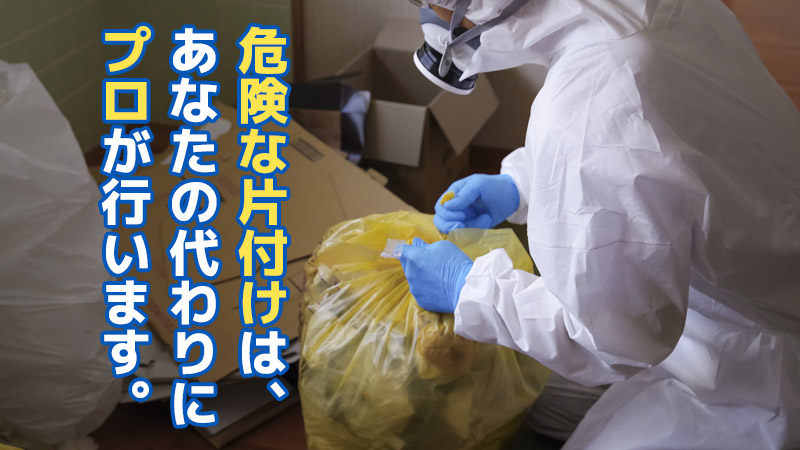
ゴミが長期間溜まり、腐敗や害虫が発生している重度の状態。
ここまで進行すると、マスクや手袋では防ぎきれない衛生リスクが伴います。
「申し訳なくて業者の人を呼べない」とためらう方も多いですが、この段階では自力での片付けは危険です。
感染症やガス発生の恐れがあるため、ゴミ屋敷片付けの専門業者による清掃が必要になります。
お部屋の状況イメージ
- ゴミや食べ残しが腐敗して悪臭が発生
- ハエやゴキブリなどの害虫が多発
- 壁や床が汚染されている
- 清掃費用は20万〜30万円が目安(※状況により異なる)
片付けのコツ(依頼前の準備)
- 無理に触らず、現場の写真を撮るだけでOK
- 「残したい物・探したい物」をメモしておく
- 専門業者に見積依頼時、写真と間取りを送付するとスムーズ
- 悪臭・虫害がある場合は、消臭・防虫の相談をする
ポイントアドバイス
プロの業者は、現状の部屋を責めることは絶対にありません。
清掃後は「空気が変わった」「ここからまた暮らせる」と涙ぐむ方もいらっしゃいます。
片付けることは、生活を取り戻すこと。
その第一歩を、安全に踏み出すために、専門の力を借りましょう。
ゴミ屋敷は放置しておくとリスクしかありません。
ゴミ屋敷のリスクについては、詳しくは以下の記事に記載しています。
2.自力でできる片付けステップ
「よし、片付けよう!」と思っても、いざ目の前にゴミの山があると、どこから手をつけていいかわからなくなってしまうものです。
でも大丈夫。片付けは“勢い”ではなく、“順番”が大切です!
ここで紹介する5つのステップを意識するだけで、無理なく現状を改善することができます。
STEP 1:まずは“現状を把握”する
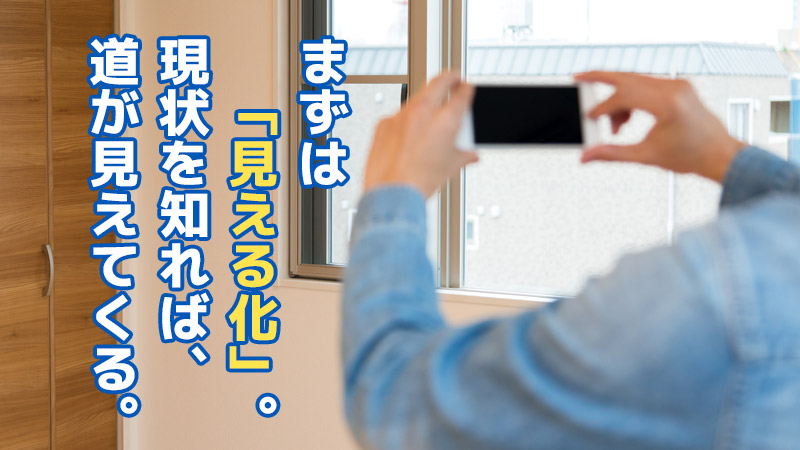
いきなり手を動かすのではなく、まずは「部屋の状態を把握」しましょう。
スマホで写真を撮るのもおすすめです。
客観的に見ることで、「どこが一番ひどいか」「どこから片付けるか」が見えてきます。
やることリスト
- 各部屋・スペースを写真に撮る
- ゴミの種類をざっくりメモ(燃える/不燃/リサイクルなど)
- 自分一人でできる範囲を考える
STEP 2:ゾーンを決めて小さく始める
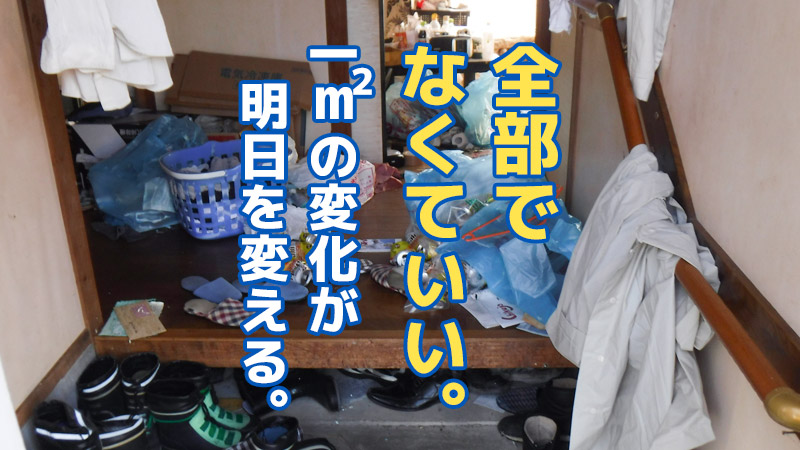
“全部片付けよう”と思うと挫折する
一番多い失敗が「一気に全部やろうとする」ことです。
実は片付けは、小さな成功体験の積み重ねが一番効果的です。
おすすめの始め方
- 「玄関から1m」「ベッドの周りだけ」など範囲を決める
- タイマーを30分かけて、時間を区切る
- 片付け前後の写真を撮ってモチベーションUP!
STEP 3:仕分けルールを明確にする
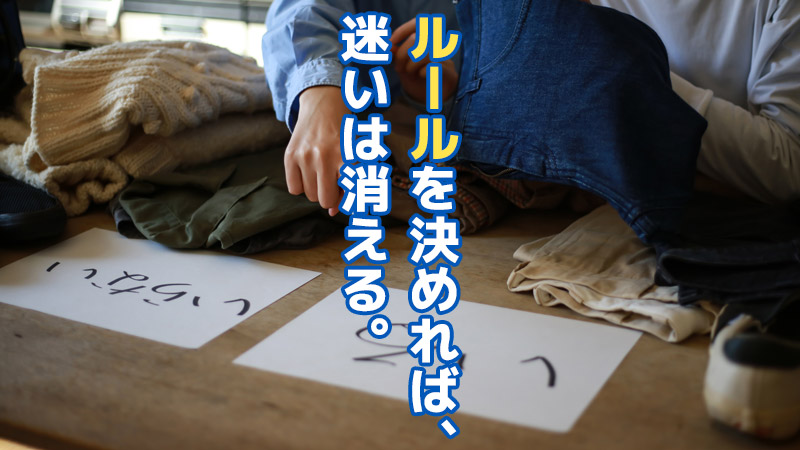
捨てる・残すの判断を迷わないために
「いつか使うかも…」で止まると、片付けは進みません。
プロの現場でも活用しているのが、3分類ルールです。
| 分類 | ルール | ポイント |
|---|---|---|
| 残す | 今使っている/今後必ず使う | 収納場所を決める |
| 保留 | 迷ったもの/一時的に保管 | 箱に入れ“1か月後に再判断 |
| 捨てる | 壊れている/1年以上使っていない | 躊躇せずゴミ袋へ |
分類を決めておくと、片付け作業がスムーズに進みます!
STEP 4:分別と搬出の計画を立てる
“一度に出せない”を防ぐために
自治体ごとにゴミの出し方や日程が異なります。
せっかく仕分けしても、ゴミが出せないと再び散らかる原因になってしまいます。
ポイント
- 自治体のゴミカレンダーを確認
- 粗大ゴミ・家電リサイクル品は早めに予約
- 搬出が難しい場合は、一部だけ業者回収を併用する
STEP 5:片付け後の“維持ルール”を作る
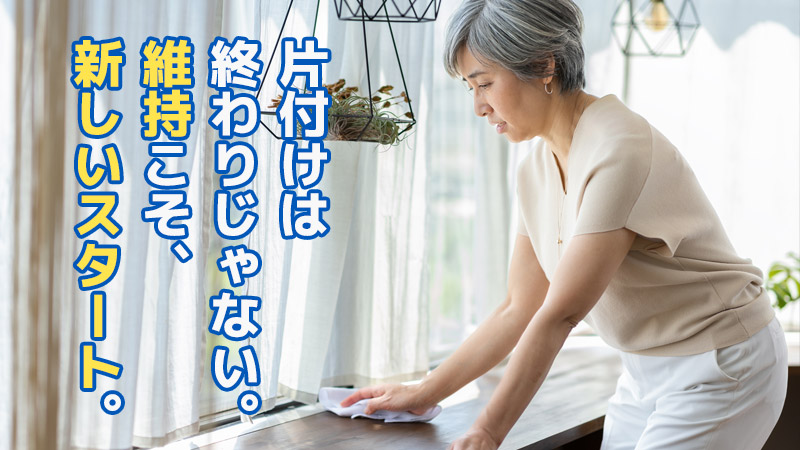
リバウンド防止は「ちょっとした習慣」で決まる
せっかく片付けても、数週間で元通り…という人も少なくありません。
そこで大切なのが、リバウンドしない仕組みづくり!
維持のコツ
- 「出したら戻す」「1日10分片付け」などシンプルなルールを決める
- 新しいモノを買う時は“1つ入れたら1つ捨てる
- 月に1回、写真を撮って状態を見直す
プロからのアドバイス
片付けは“きれいにすること”が目的ではありません。
自分の暮らしを取り戻す、人生のリセットでもあります。
「やらなきゃ」ではなく、「ここから変われる!」と思って、できる範囲から始めてみましょう。
3.どこまで自力?業者を頼む判断基準とは
「やる気はあるけど、限界を感じたらプロの出番です。」
「自力で片付けたい」と思うのは素晴らしいことです!
でも、部屋の状態やゴミの量によっては、プロに頼んだ方が安全・確実なケースもあります。
ここでは、プロ目線で見た「頼むべきタイミング」と「判断の目安」を紹介します。
判断①:ゴミの量が“自分の体力・時間”を超えている

“時間と体力のコスパ”を考えてみよう
ワンルームでも、膝までゴミが積もっている状態になると、45Lゴミ袋で30〜50袋以上になることも珍しくありません。
- 週末だけでは終わらない
- 分別に何時間もかかる
- 運び出すだけで疲れてしまう
そんなときは、業者に「分別と搬出だけ」でも依頼するのがおすすめです。
片付けの主導権はあなたにありながら、時間と労力を削減できます。
判断②:悪臭・害虫・汚れがある場合
“掃除”と衛生処理”の領域です
腐敗臭やカビ臭が強い、害虫が発生している場合は、家庭用洗剤やマスクでは健康被害のリスクが生じます。
特に注意すべきサイン
- ゴミが湿っている/液体が出ている
- ハエ・ゴキブリ・ダニが大量発生
- 壁や床にしみ・カビ跡
この状態は、もはや“清掃”ではなく“特殊清掃”が必要になります。
専門装備と消毒・脱臭処理が必要なため、早めに業者へ相談することをおすすめします。
判断③:精神的に手が止まる・やる気が続かない
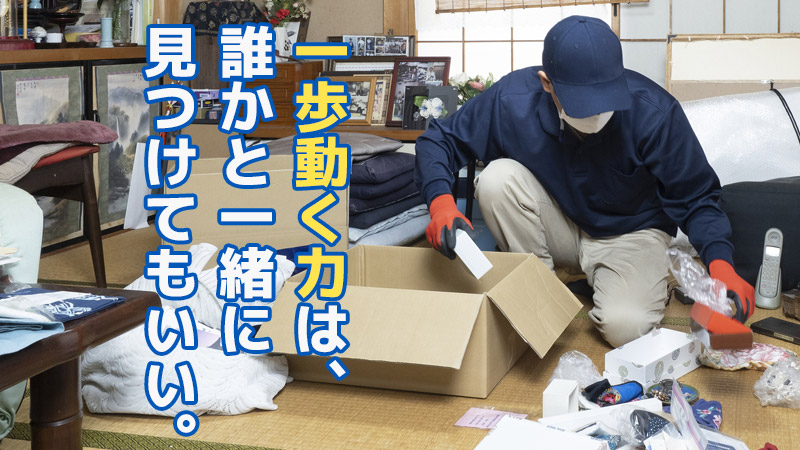
“心が動かない”ときこそ、外の力を借りるタイミング
「やらなきゃ」と思っても、部屋に入ると気が重くなる。
これは、片付け疲れや自己否定感が積み重なっているサインです。
そんなときは、プロに初期整理だけ依頼してみましょう!
スペースが少しでも空くと、気持ちに余裕が生まれ、「ここから自分でやってみよう」と思えるようになります。
判断④:大型家具・家電が処分できない
“持てない・運べない”ものはプロに任せよう
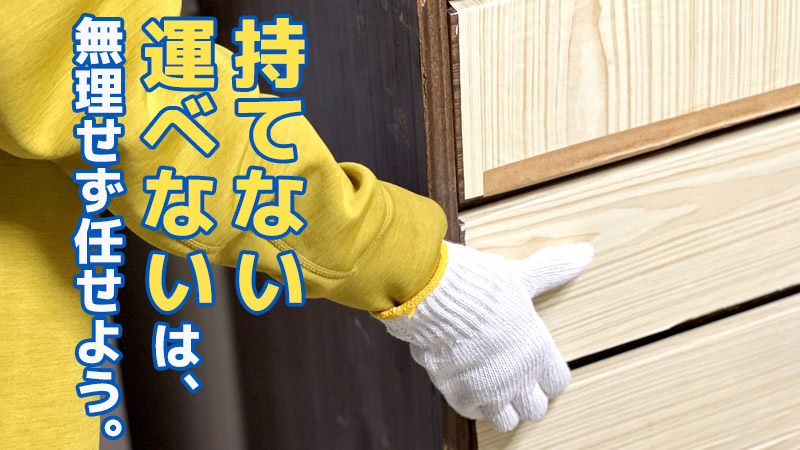
冷蔵庫・洗濯機・タンスなどの大型品は、自治体に処分を依頼しても、搬出は自力です。車両が必要になる場合もあります。
業者に頼めば、
- 解体・搬出・処分を一括対応
- 家屋や階段を傷つけずに安全搬出
- 買取可能品はその場で査定
というように、時間と手間を大きく省くことができます。
判断⑤:引っ越し・退去・親族対応など、期限がある場合

期限がある片付けは“スピード勝負”
退去や引っ越し、親族宅の片付けなど、「〇日までに」が決まっている場合は、迷わずプロに相談を!
プロの専門業者なら
- 作業日程を一括で調整
- ゴミの種類や搬出経路もスムーズ
- 必要に応じて清掃・消臭まで完了
「終わらないかも」という不安からも解放されます。
まとめ:頼るのは“最後の手段”ではなく、“前に進むための選択肢”
片付けには、「頑張る」以外にも、いくつもの正解があります。
ゴミ屋敷の片付けは単なる「掃除」ではなく、自分の暮らしや気持ちを立て直すための再スタートです。
「片付けなきゃ」「どうしてできないんだろう」と、自分を責めてしまう人も少なくありません。
でも実際には、部屋が散らかるのは“怠け”ではなく、仕事の多忙さや心の疲れ、思い出の整理が追いつかないなど、誰にでも起こりうる自然なことです。
自分のペースで進めることが、いちばんの近道
ゴミ屋敷レベル1〜4のステップを見てきたように、「できるところから少しずつ」で十分です。
最初の1袋を出すこと、通路を作ること、その一歩が、次の動きにつながります。
焦らず、比べず、自分のペースで。
もし手が止まってしまったら、“誰かの手を借りる”という選択もあります。
それは「頼る」ことではなく、
“自分の暮らしを守るための行動”です。
ゴミ屋敷清掃20年以上のプロの視点からひとこと
片付けは、モノを減らすことではなく「心を軽くすること」。
無理をせず、助けを借りながら進めても、それは立派な“自立”です。
ゴミ屋敷の片付けに「遅すぎる」ことはありません。どんな状態でも、始めた瞬間から前に進んでいます。今日、この記事を読んだあなたは、すでに片付けへの第一歩を踏み出しています!