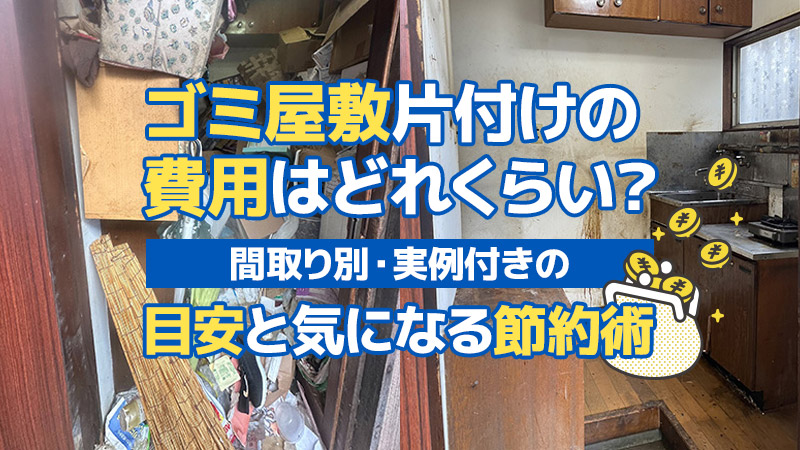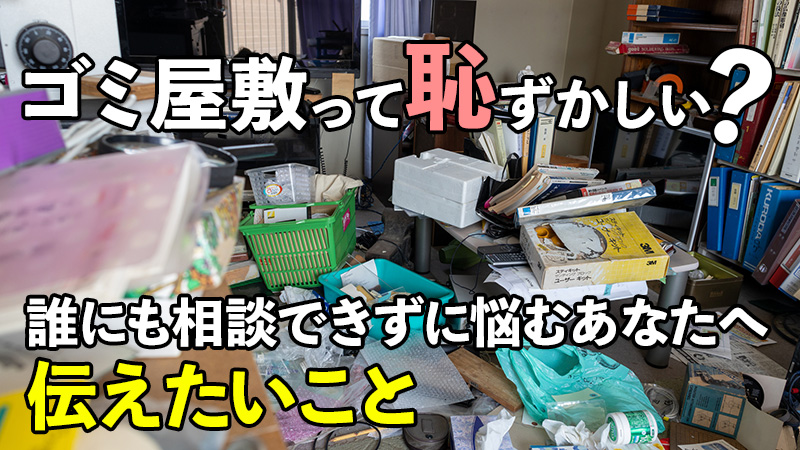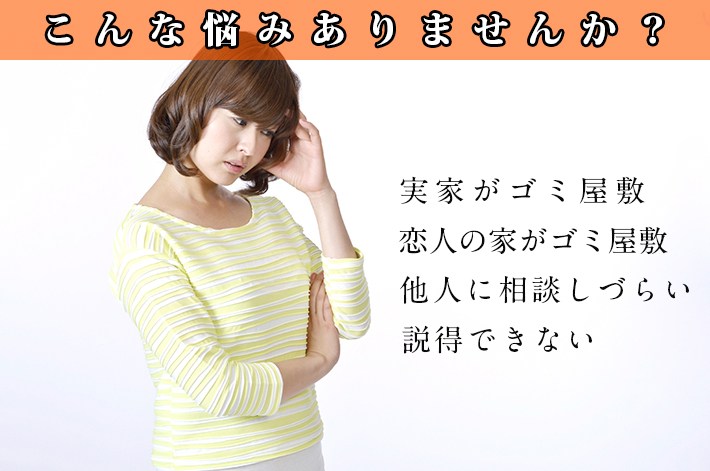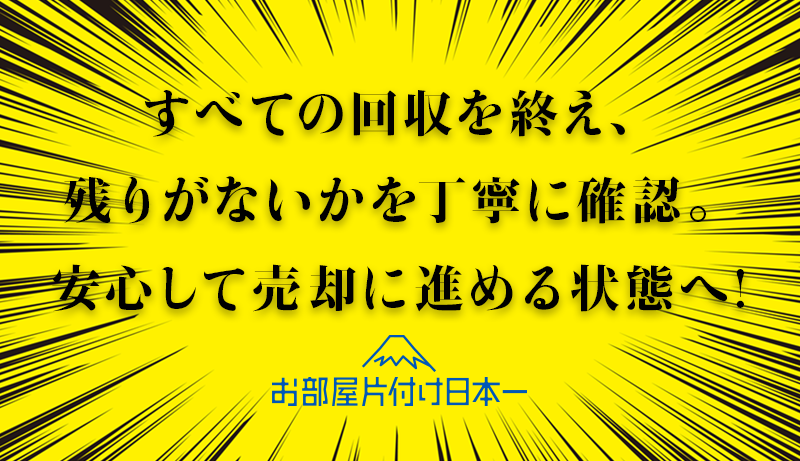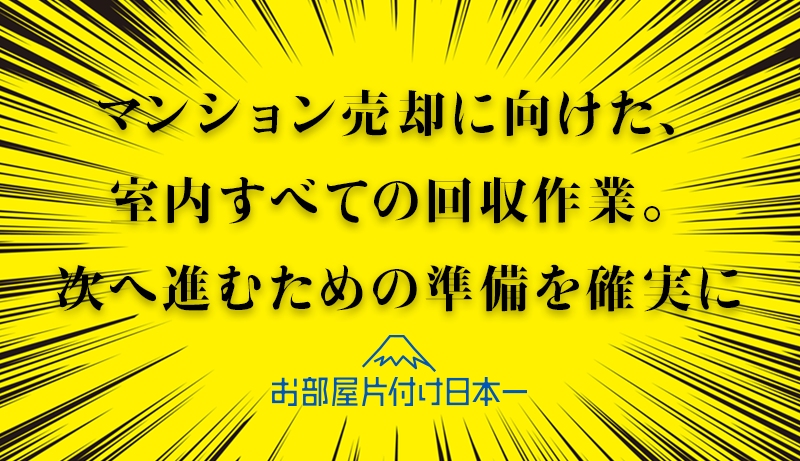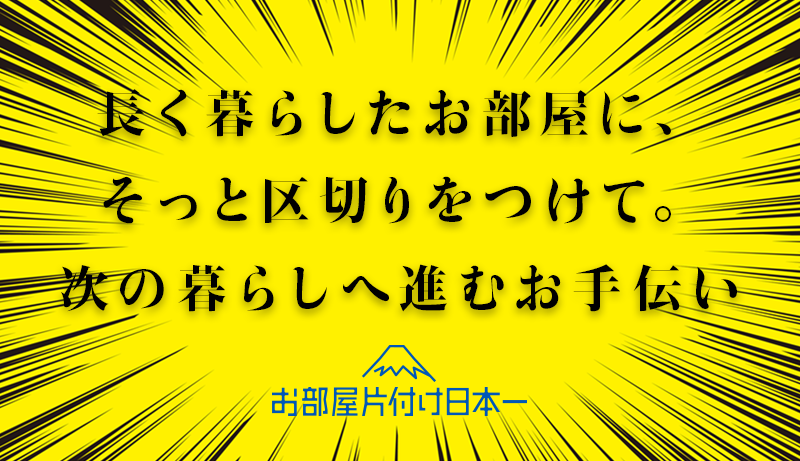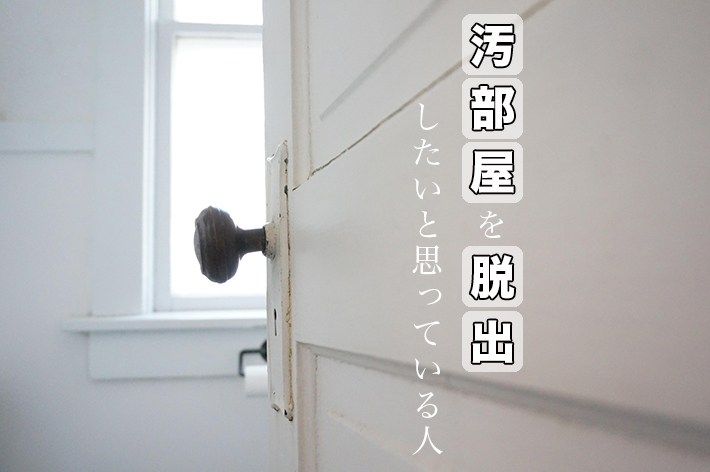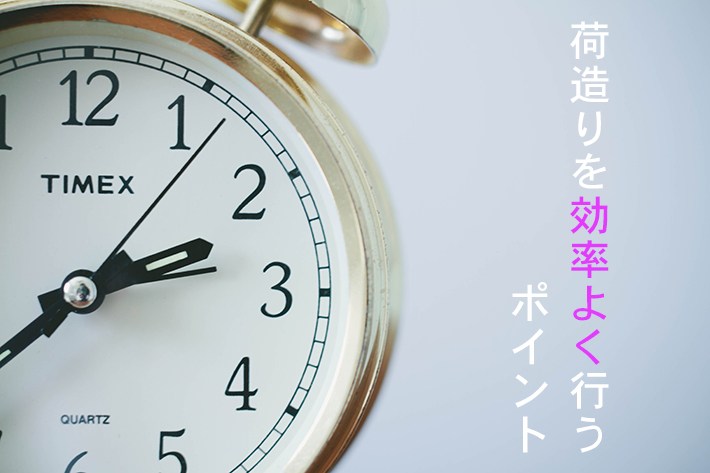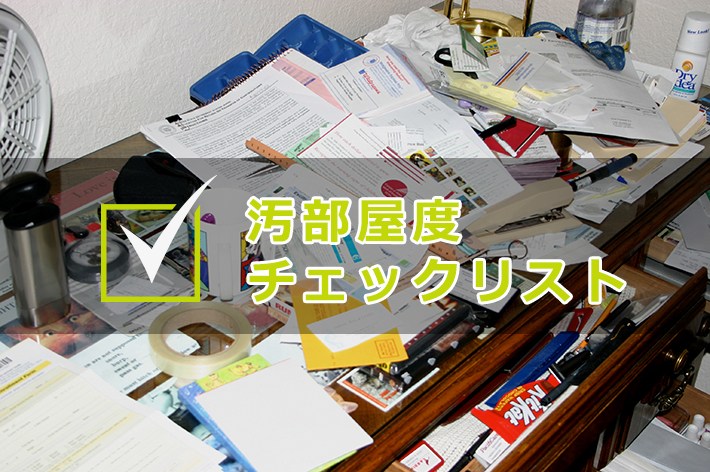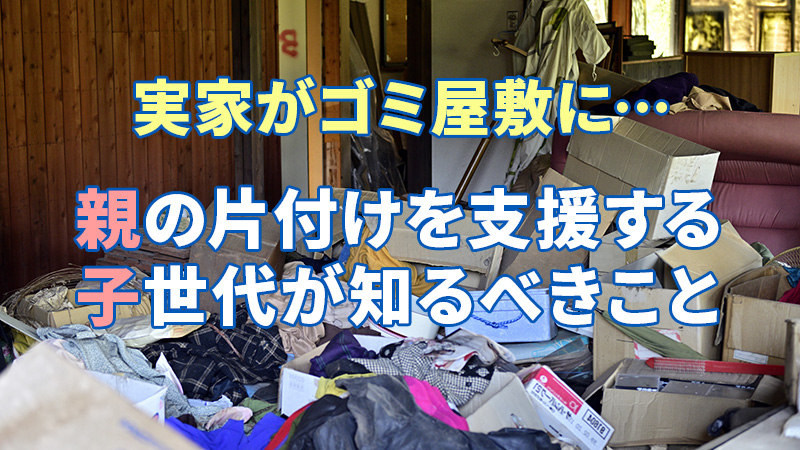
目次
1. はじめに|実家が気になり始めたあなたへ。片付けサポートの第一歩
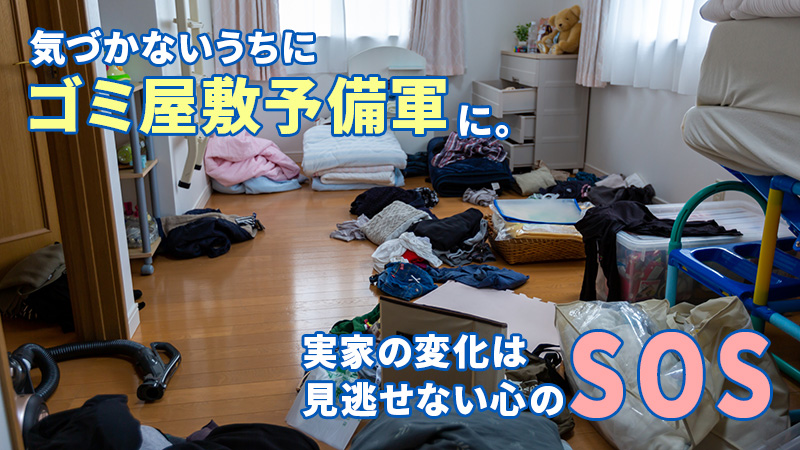
久しぶりに実家に帰ったとき、ふとこんなことを感じたことはありませんか?
- 「前より物が増えている…?」
- 「なぜか片付いていない場所が多い」
- 「郵便物が山積みになってる?」
- 「ゴミの日を忘れているみたい…」
- 「キッチンの洗い物がずっと残っている?」
それはもしかすると、“実家がゴミ屋敷予備軍”になっているサインかもしれません。
そして実は、「親にどう声をかけていいかわからない」「勝手に片付けるわけにもいかない」と悩んでいる方は、あなただけではありません。
家族の片付け問題は、誰にとってもデリケートで、気をつかうものなのです。
この記事では、親世代の片付けをサポートするために、子世代ができることを心理的な配慮と具体的な行動の両面からわかりやすくお伝えしていきます。
もし、すでに実家がゴミ屋敷状態になっていたとしても、焦らなくて大丈夫です。
解決の選択肢はちゃんとあります。
まずは、以下の3つのポイントを意識して、信頼できる専門業者に相談するところから始めてみましょう。
相談時に気をつけたい3つのポイント
- 安心して任せられる専門業者かどうか(実績・在籍スタッフ・女性対応の有無など)
- 必ず相見積もりをとること(面倒でも、価格比較や接客対応の差が見える)
- 極端に安い業者には注意(あとから高額請求されるケースもある)
それでは、本題となる「親の片付けをどう支援するか」について、詳しくご紹介していきましょう。
2. 実家がゴミ屋敷になりやすい理由とは?
親世代、特に高齢の方の住まいがゴミ屋敷化しやすいのには、複数の背景要因があります。
以下は、現場でもよく見られる代表的な理由です。
- ① 体力の衰えで片付け作業が負担に
-
年齢とともに、かがんだり、重い物を持ったりする作業が徐々に難しくなります。
ゴミをまとめて袋に詰める。
ゴミ捨て場まで運ぶ。このような日常動作も、高齢者にとっては「毎回がひと苦労」なのです。
「やらなきゃ」と思っていても、腰痛や関節痛、体力の低下で動けない。その結果、少しずつ物が積もり、いつの間にか手がつけられなくなっていくケースが非常に多く見られます。
- ② 認知機能の低下で“片付けの優先順位”が後回しに
-
「今日は何曜日だったかな?」
「このゴミ、捨てるんだっけ?」このように、軽度の認知機能の変化が起きると、ゴミの分別や収集日に間に合わせることが難しくなり、出しそびれたゴミが積もることがあります。
また、「片付けよう」という意識そのものがぼやけてしまうこともあり、悪気がないままゴミが放置されてしまうのです。
- ③ “もったいない精神”が根強く、物を手放せない
-
「まだ使える」「誰かが使うかも」
そう思って取っておいたものが、気づけば部屋を占拠している。
戦後の物がない時代を生きてきた親世代にとって、“捨てる”という行為には強い抵抗感があります。
その結果、使っていない家電、衣類、空箱、紙袋などが積み重なってしまうのです。
- ④ 社会的な孤立により、相談や支援のハードルが高い
- 高齢になると、友人・近所付き合いが減り、「ちょっと相談できる人」がいなくなる傾向があります。
また、「子どもに迷惑をかけたくない」という遠慮から、本音を言えないまま、困りごとを抱え込んでしまう方も少なくありません。
こうした複数の要因が絡み合うと、本人も「片付けなきゃ」と思いながらも、どうしていいかわからず、“問題を見ないようにする”ことで心のバランスを保とうとしてしまうことがあります。
特に高齢者の場合、「できないけれど、できないと言えない」ことがとても多く、結果として、ゴミ屋敷化が深刻になってから初めて発覚する。というケースが珍しくありません。
3. こんな兆候は危険信号|親の“片付けられないサイン”
「実家はまだ大丈夫だと思っていたけれど、よく見ると気になる点が…」
そんな“ちょっとした違和感”が、ゴミ屋敷化の初期サインであることは意外と多いのです。
特に高齢者は、「片付けなければ」と思いながらも、体力・気力・判断力の面でそれを実行に移せないことがよくあります。
以下のような兆候が見られたら、“片付けられない”ではなく、“片付ける余力が残っていない”という状態を疑ってみてください。
- ① よくある“片付けられないサイン”
-
- ゴミが何日も出されていない(ベランダ・玄関・廊下に袋ごと放置)
- キッチンの流しに食器が溜まりっぱなし(洗って使う習慣が失われている)
- 郵便物・チラシが山のように溜まり、未開封のまま
- 床にモノが散乱していて歩きづらい(転倒リスクもあり非常に危険)
- ペットボトル・空箱・紙袋など“何かに使うかも”が放置されている
- 脱ぎっぱなしの衣類が部屋に置きっぱなしになっている
- 冷蔵庫の中が腐敗・カビなどで手つかずの状態

- ② こんな親の言葉があれば注意かも!?
-
- 「また今度やるから」
- 「私のやり方があるの」
- 「ゴミじゃないの、それ」
- 「誰も来ないんだから別にいいでしょ」
こうした発言は、「気にしてない」のではなく、“どうしていいか分からない”ことの裏返しであることが多いです。
小さな違和感が、未来を大きく変えます。
たとえば郵便物の山、捨てられない空き容器、片付けを拒むような言動。
どれも些細なことのように見えて、積み重なると生活機能そのものが崩れていくリスクがあります。
このような“変化の兆し”に早く気づいてあげることが、家族としてできる最も大きなサポートの一歩です。
4. 声のかけ方で変わる!親に伝えるときのポイント
実家が片付いていないと気づいたとき、つい口から出てしまいがちな言葉があります。
- 「片付けた方がいいよ」
- 「こんなに汚くしてどうするの?」
- 「ちゃんとしてよ!恥ずかしいよ」
でも、こうした言葉は、親の心を閉ざす“きっかけ”になってしまうことが多いのです。
高齢の親にとって、“片付けられない”のは、単なる怠けではありません。
その背景には、「体力的にしんどい」「何から始めたらいいか分からない」など、不安や無力感が潜んでいます。
だからこそ、“正論”より“共感”が大切です。
片付けに対する“恥ずかしさ”や“防衛反応”を刺激しないよう、言葉のトーンや順序がとても大切になります。
親に伝えるときの3つのポイント
- 責めない
- 命令しない
- 寄り添う
言い換えれば、「一緒に考えよう」「安心して任せてほしい」という姿勢が伝わることが重要です。
伝え方の実例フレーズ
- 「最近、足元危なくない?転ばないか心配なんだ」
- 安全への配慮を軸に話すと、素直に受け入れやすい。
- 「一緒に使いやすくしたら、もっと楽になるかもしれないよ」
- “ラクになる”という言葉は、高齢者の心の負担を和らげる。
- 「昔よく使ってた道具とか、写真とか、また一緒に見たいな」
- “捨てる”ではなく、“思い出を一緒に探す”という提案に変える。
- 「大事なものは残そう。いらないかどうか、一緒に決めてみよう?」
- 自分で選ぶ権利を残すことで、安心感が生まれる。

なぜ“思い出”や“安全”の視点が有効なのか?
親世代は「捨てる=否定される」「誰かに家を見せる=恥ずかしい」と感じがちです。
でも、“怪我をしないため” “昔の思い出を大切にするため”という理由なら、「片付けることに意味がある」と、前向きに捉えてもらえる可能性が高くなります。
5. 親が片付けを拒否する心理とは?
「片付けよう」と声をかけても、親があからさまに拒否する。
または、
「そのうちやるよ」と言いながら、何もしないまま日々が過ぎていく。
そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
でも、そこには単なる“わがまま”や“怠慢”ではない、複雑な心理的背景が隠れていることがほとんどです。
親が片付けを拒む主な心理
- 「捨てたら思い出まで失われそう」
- モノには、“人生の一部”が詰まっていると感じている。
- 「他人に家を見せたくない」
- 汚れた部屋を見られる=自分の人生を否定されるようで怖い。
- 「自分のやり方を否定された気がする」
- 長年の生活スタイルを急に変えることに強い抵抗がある。
- 「今さら片付けても意味がない」
- 年齢や体調による無力感から、あきらめに似た感情がある。
これらの心理は、「過去への執着」と「老いへの不安・自己防衛」が入り混じったものです。
片付けの話題になると、親が急に機嫌を悪くしたり、黙り込んだりするのは、その奥にある“傷つきたくない気持ち”が反応しているからなのです。
大切なのは「気持ちを否定せず、共に進める姿勢」
「なんでこんなに物が多いの?」
「こんな汚い部屋、恥ずかしくないの?」
これらは、親にとっては“人格そのものを否定された”ように感じてしまう言葉です。
片付けとは、ある意味で“人生の整理”に近い行為。
それを他人に指示されるのは、とてもデリケートなことなのです。
心を溶かす声かけのヒント
- 「一気にやらなくていいよ。今日は1か所だけにしようか?」
- 「これは使う?思い出があるなら、ちゃんと残しておこう」
- 「昔のお弁当箱、まだ取ってあるんだね。懐かしいね」
- 「お母さん(お父さん)のペースでいいよ。無理にとは言わないからね」
少しずつでいい。“理解してくれる人がいる”と伝わるだけで、心の壁がほんの少し、柔らかくなるのです。
6. サポートの進め方|家族でできること・プロに頼るべきこと
親の家が片付かないと気づいたとき、「全部自分でなんとかしなきゃ」と思い込んでしまう方が多くいらっしゃいます。
ですが実際には、“家族でできること”と“プロに任せた方がよいこと”を切り分けて考えることが大切です。
無理をしすぎず、できることから少しずつ取り組む。
それが、親子関係を壊さずに片付けを進める一番の近道です。
家族でできること|“心の距離”を縮めるアプローチ
- 1.親と一緒に小さな範囲を片付けてみる
- たとえば「今日はこの引き出しだけ」「紙袋を3つだけ整理」など、成功体験を積み重ねることで、片付けへの自信を回復させる。
- 2.片付けの時間を“行事”にする
- 「母の日掃除」「父との月1整理DAY」など、特別な日として明るく取り組む。
“指導”ではなく“イベント”にすることで、親の抵抗が薄れる。
- 3.親の話にじっくり耳を傾ける
- 片付け作業よりも、「なぜ捨てられないのか」「どんな思いがあるのか」をしっかり聞くことで、信頼関係が深まり、親の態度が軟化することも。
プロに頼るべき場面|“安心・安全・効率”を考慮して
- ゴミや物が多すぎて、家族だけでは手に負えないとき
- 害虫や悪臭が発生しているなど、衛生面に不安があるとき
- 家族が感情的になってしまい、かえって関係が悪化しそうなとき
こういった場合は、迷わず専門業者への相談をおすすめします。
たとえば、お部屋片付け日本一では
- 女性スタッフ対応(親御さんが安心しやすい)
- LINEで写真を送るだけで概算見積もりをお送りしますので、手軽に費用感がわかる
- 作業前に丁寧なヒアリング・下見あり
など、ご家族の気持ちに寄り添うサポート体制を整えています。

サポートの基本は、「背中を押すこと」「頼れる環境を整えること」
「手伝う」といっても、すべてを自分で片付ける必要はありません。
むしろ、親の“やる気”や“安心感”を引き出すことのほうが大切です。
- 一緒に取り組むこと
- 聞く耳を持つこと
- 必要に応じて外部とつなぐこと
それが、“家族にしかできない”サポートなのです。
7. 片付けで変わった実例|親子の距離が縮まったAさんの声
Aさん(50代女性・都内在住)は、昨年末に久しぶりに実家へ帰省した際、キッチンに足を踏み入れて驚いたといいます。
「シンクの中は使い終わった鍋や食器でいっぱい。
足元には買い物袋が積み重なっていて、“あれ、こんなに物が多かったっけ?”と、違和感が一気に押し寄せました」
母親は明るく迎えてくれたものの、どこか落ち着かない様子で、「そのへん座っちゃって」と言いながら、あちこちのモノをどけていたようです。
片付けを切り出せなかった理由は?
「最初は“手伝おうか?”とも言えなかったんです。
母が怒るかも、傷つくかも、って考えたら何も言えなくなってしまって」
そんなAさんでしたが、帰宅後に思い切って「片付けを一緒にしたい」「でもお母さんの気持ちも大切にしたい」と伝えるLINEをお母様へ送ったようです。
母の返事はこうでした。
「ありがとう。でも、どこからどうしたらいいか分からないのよ…」
“写真1枚”から始まったプロへの相談
Aさんは悩んだ末に当社へLINE相談をしてくださいました。
実家の様子を撮影し、数枚の写真と簡単な説明が届きました。
詳しい状況の確認やご不明な点等のご説明を含め、私(綾部)による訪問見積もりが決まりました。

作業当日。思い出の品がつないだ親子の時間
片付け作業は2日間にわたって行いました。
当社スタッフが1つ1つ声をかけながら仕分けを進めていくうちに、お母様は次第に口数が増え、「この鍋、昔お父さんと買ったのよ」と懐かしそうに語り始めたといいます。
Aさんは振り返ります。
「物が減るごとに、空気も軽くなっていく気がしました。
母の表情も、なんだか少し明るくなっていて──
こんなにゆっくり、2人で話したのは久しぶりだったかもしれません」
片付けが終わったあと、母のひとこと
作業完了後、白く輝くキッチンを見ながら、母がぽつりとつぶやきました。
「……これで、またご飯つくれるかもしれないね」
Aさんはその言葉に、行動に移して本当に良かったと話します。
このように、片付けは「モノを捨てる」こと以上に、
“親子の関係性を再構築する”大きなきっかけにもなり得るのです。
8. まとめ|親も、自分も、心地よく暮らすために
ゴミ屋敷という言葉の裏側には、片付けられない状況に悩み、でも誰にも言えずに抱え込んでいる“誰か”がいます。
それが、あなたの親かもしれません。
片付いていない部屋には、健康や安全面のリスクも潜んでいます。
- 転倒による骨折
- 食品の腐敗による体調不良
- 害虫・カビ・悪臭などによる住環境の悪化
- 火災リスク(コンセント周辺の埃、新聞紙の堆積 など)
だからこそ、“まだ大丈夫かな?”と感じた今が、最初の声かけのタイミングです。
行動の一歩は、愛情のかたち
お子さんが「気になってるよ」「一緒に片付けてみようか」と言葉をかけるだけで、親御さんの表情がふっと緩む瞬間を、私たちは何度も見てきました。
親世代は、“頼ることが下手”な方がとても多いんです。
だからこそ、お子さんが“気にかけてくれてる”ことが伝わるだけで、表情がふっと柔らかくなる瞬間に、私たちは何度も立ち会ってきました。
片付けは、家族の愛情の形でもあります。
どうか、安心してご相談ください。
あなたのその“気づき”が、親御さんにとっての希望になります。
片付けを通して、親の暮らしが少しでも快適に、そして親子の距離が少しでも近づいていく。
そんな未来のきっかけが、このページで見つかったなら、本当に嬉しく思います。